| :冒険家としての環境論 (2005/02/09)
 三年にわたり毎夏モンゴルを旅したことがある。一人で行くのが困難な場所なので、モンゴル・ラリーのインターネット・リアルタイム報道員として同行した。道具はデジカメとパソコンとインマルサット(衛星回線)で、夜になると星降る草原に座り当日のラリー結果をインターネットに送るのが仕事だった。キャンプからキャンプへとラリーコースに沿ってテント生活が半月ほど続く。 三年にわたり毎夏モンゴルを旅したことがある。一人で行くのが困難な場所なので、モンゴル・ラリーのインターネット・リアルタイム報道員として同行した。道具はデジカメとパソコンとインマルサット(衛星回線)で、夜になると星降る草原に座り当日のラリー結果をインターネットに送るのが仕事だった。キャンプからキャンプへとラリーコースに沿ってテント生活が半月ほど続く。
移動はヘリなのでキャンプ周辺を探索するには十分すぎる程の時間があった。そんなある日、牛飼いの少年が200kmで草原を飛ばすラリーカーを指差して「あんなに急ぐ意味あんの?」と言ったのがきっかけでラリーに興味を失った。僕はそのかわり有り余る時間を利用してゴビ砂漠を単独縦断したり、原住民と馬に乗って騎馬民族のような生活を楽しむようになっていった。
モンゴルというところは草原の草が数キロ先からなびいてくるのを見て風が吹いてきたことを知る草原世界だ。高山植物の宝庫で、テント周辺ではエーデルワイスが雑草のようにあたり一面に咲き乱れていた。
遊牧民なのでゲルと呼ばれるテントを住居にして、羊に与える新鮮な草を求めて年に数箇所を移動生活する。同じところに移動することはないから手紙を送ることはできない。彼らに「住所は?」と尋ねてみたら「なんのことだ?」と返された。「君の土地はどこにある?」と尋ねたら「全部さ」と地平線から地平線までを大きく手で円弧を描いて見せてくれた。それどころか例えば道に迷った人が留守中のゲルにある食料をかってに食べても何も言わないし、むしろ「よく来た」と歓迎してくれる。というのは冬になると氷点下の凍てつく平原になり、迷うことは死を意味する。そんな世界では生き延びる手段は助け合うということなのだ。
食料は羊だ。あるときご馳走するといって若者がもてなし料理をするために一匹の羊を連れてきた。そのとき羊は観念している様子で優しい目をしているのが印象的だったのだが、若者がナイフで心臓をスーッと刺すと羊は眠るように死んだ。それから彼は皮、骨、内臓、肉とまるでプラモデルを分解するように、わずか七分でばらばらにした。皮はお母さんがなめし、内臓は娘がしごいて腸詰め袋にし、肉は長老が公平に分けた。殺した羊の血の一滴までも無駄にはしない見事な生活の知恵そのものだった。
モンゴルの草原にはコンビニもガソリンスタンドも、店というものがない。物質を買うということが必要ないので金を稼ぐことも争うこともない。彼らは羊に新鮮な草を与えるために遊牧し、羊の乳を飲み、羊を食し、羊を着る。人間は死ねば野ざらしにして鳥の食料になる・・・という完璧な食物連鎖が、数千万年にわたり人間と生き物の共存を維持してきた。その中にあって初めて人間は何を作り、何を使っていくべきなのかを理解できるのではないだろうか。
夕方になるとゲルから夕食支度の湯気があがり、お母さんが子供をしかる声が聞こえ、お父さんは羊と馬の見回りをする。幸せとはこのことだ、と強く教えられた日々だった。冒険という挑戦、ラリーという競争では知ることができなかった人間らしい幸福を改めて大切に思う瞬間だった。
NTT東日本「Solution TODAY」vol.23掲載
発行:NTT東日本千葉支店
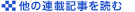
|
